今回はインフレ、デフレ、スタグフレーションについてお話しします。
日本はデフレの時代と言われてきましたが、2020年ごろからインフレに突入し、物価も上がりました。
しかし、インフレは良いインフレと悪いインフレがあります。
いま日本で起きているインフレは悪いインフレであり、良いインフレと悪いインフレの違いをきちんと理解しておくと、インフレが起きた時の対応をどうすればいいかが分かります。
今回はインフレ、デフレ、スタグフレーションについてお話しします。
目次
インフレとは? 良いインフレと悪いインフレの存在について
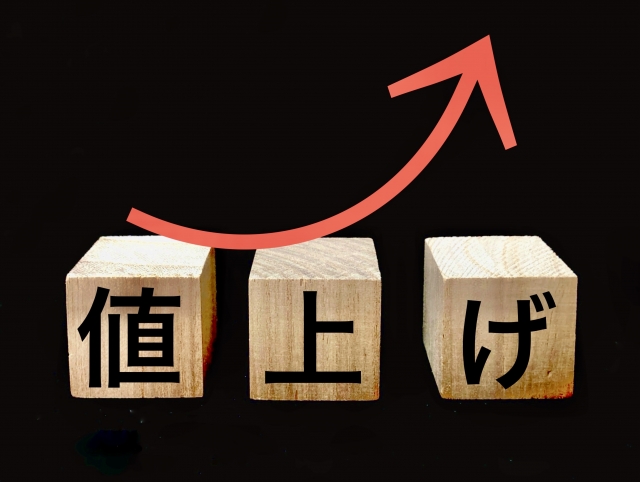
インフレとは物価が上がり、お金の価値が下がる現象のことです。
例えば100円で買えていたものが110円出さなければ買うことが出来なくなることです。
これが、一つの企業の物価だけではなく、日本全体の企業で同じことが起きます。
インフレには原因により2種類のインフレがあり、1つめはコストプッシュ型インフレ、2つめはディマンドプル型インフレです。
コストプッシュ型インフレとは材料等のコストが掛かることで物価が押し上げられること。
2024年の日本で起きているインフレはまさにこれです。
強い円安の影響等により海外から輸入する材料のコストが上がり、そこに燃料のコストも上がったことで、物価が上がりました。
このインフレは良いインフレと悪いインフレのどちらかであるかというと悪いインフレということが出来ます。
なぜなら、材料代などのコストが上がることで、従業員の給料に反映されないからです。
そのため、物価だけが上がって給料が上がらない状況となり、生活が苦しくなることで商品の買い控えが起きることで、景気が悪くなることが懸念されます。
コストプッシュ型のインフレは後述するスタグフレーションに移行する可能性があり、早期に手を打たないと経済はどんどん悪化します。
本来であれば、政府が財政出動することでコストプッシュ型のインフレを抑制しなければなりません(本来であればこのために税金を払っているのですが、政府は海外にお金をばらまくだけで日本の問題に対しては何もしてきませんでした)が、日本では何もしないどころか逆に国民の負担を増やすという、どう考えても頭のおかしいことをやってきたため、コストプッシュ型のインフレが起きたままでさらに景気が悪化するようになってしまいました。
確かに円安により輸出企業や外貨を稼ぐ企業は活気が出ましたが、それを日本の内需に頼る企業に還元できなかったことも一つの問題だったと言えるでしょう。
一方でディマンドプル型のインフレは、景気が良くてモノが良く売れることから、需要と供給のバランスが取れなくなり物価が上がるインフレとなります。
コストプッシュ型インフレは不景気の時に起こる(実際に2024年の日本がこれを証明しています)のですが、ディマンドプル型のインフレは好景気の時に起こります。
ディマンドプル型のインフレでは輸入する材料などのコストには変化がなく、モノが売れる分賃金に還元できるため、更なる購買力の促進につながります(材料の仕入れ額はインフレにより上がっていきますがそれ以上にモノが売れるのでディマンドプル型インフレが続いている限り企業が苦しくなることはありません。これがコストプッシュ型インフレに変わると企業が苦しくなります)。
一般に良いインフレと言われるのはこちらのディマンドプルインフレのことであり、経済成長とともに物価が上がってきたのはディマンドプル型のインフレが起きたためと言うことが出来るでしょう。
デフレとは何か? 日本ではデフレが続いていたと言われていたが?

デフレとは物価が下がり、お金の価値が上がる現象のことです。
例えば100円で買えていたものが90円で買うことが出来るようになることで、これが1つの企業だけではなく、日本全体で起きることです。
日本は長い間デフレの時代が続いたと言われていますが、個人的にはそうは思いません。
レギュラーのガソリン代が1Lあたり100円を切り、100円でマックのハンバーガーが食べられる時はそうだったと思いますが、2010年代以降はデフレの時期だったかと言われると、疑問が湧いてしまいます。
実際に自販機で売っている100円のジュースが120円に値上がりし、今では150円になっている。
150円に上がったのはつい最近の話ですが、日本でもじわじわとインフレが起きており、ずっとデフレであったわけではないというのが個人的な意見ですね。
なぜなら、値上げのニュースは聞きますが、値下げのニュースはほとんど聞いたことがなかったからです。
聞いたことがあるのは飲食店関係とガソリン価格、ウイスキーが売れない時期位でしょうか?
それ以外のメーカーは材料のコストが下がっても物価を下げることがなかったので、日本ではそこまで強いデフレは起きていなかったというのが個人的な考え方です。
しかし、モノの値段が下がるというのは賃金が下がることにもつながります。
賃金が下がるとモノが売れなくなるため、さらにモノの値段を下げなければいけなくなる状態となり、さらに賃金に影響する。
そうなると国民の財布のひもが固くなってしまい、さらにモノが売れなくなってしまいます。
そして景気がどんどん冷え込んでいく。
このことをデフレスパイラルと言います。
2024年現在の日本はインフレに転じて、コストプッシュ型インフレにより苦しむ人が多いため、今の日本がデフレであるという意見は誤りであると言えます。
スタグフレーションとは何か? これが起きると最悪の状況
スタグフレーションとはインフレとデフレの悪い所を合わせたようなものです。
物価は上がるけど、景気が良くならず賃金も上がらない。
ちょうど2024年時点での日本がこの状況になっています。
インフレにはディマンドプル型インフレという景気を良くしていくインフレと、景気が良くないのに材料費などのコスト上昇で起こるコストプッシュ型インフレもあることをお話ししました。
コストプッシュ型インフレが起きても賃金が上がらず、物価が上がっていくため、人はモノを買い控えるようになってしまいます。
結果として景気は悪くなり、それでもインフレが進むという最悪の事態となっていくわけです。
スタグフレーションでは景気の悪化とインフレが同時進行します。
円安の影響を受けている2024年の日本がその状況であり、1ドルが110円から150円になると、アメリカからの輸入コストは単純計算でも1.36倍となります。
この分を会社のコスト削減で補填しようとしても難しく、どうしても価格に転嫁しないといけなくなります。
だから、今まで100円で買えていたものが130円に上がったり、150円に上がったりしてしまったわけです。
自販機の値段を見てびっくりした人も多いのではないでしょうか?
コカコーラの500mL入りのペットボトルが120円から180円になったりしています(2023年時点)。
それ以外でも水でも120円、お茶が150円など、もはや自販機で買う気が失せるような価格設定となっています。
また、アイスクリームの自販機を見ても昔は100円で買えていましたが、つい最近値段を見てみるとなんと180円。
自販機のアイスクリームでさえ高級品になってしまいました。
スタグフレーションを放っておくと景気がどんどん悪化してしまいますので、何か手を打たなければなりません。
2023年から2024年の時点で大手企業ではかなり賃上げが行われるようですが、中小企業ではその恩恵が回ってくるかと言うと、そうとは思えません(実際に自分が働いている会社の賃上げ額は5千円で、基本給だけだと逆に昨年より手取りが減る形となりました)。
おそらく中小企業では賃金が上がらず、人手不足で倒産となる企業が増え、下請け先のいなくなる大手企業にも影響してくるのではないかと思います。
2024年現在、政府は中小企業に対して何の対策も打たず、社会保険料の大幅な値上げとインボイス制度による実質上の増税、それに再エネ賦課金の負担増なども検討されている状態です。
今の政府を何とかしないと日本は第二のアルゼンチンとなり、金持ちとスラム街に住むガラの悪い人がいる、今までの日本ではなくなるでしょう。
スタグフレーションになると本当にまずいということはしっかり覚えておいて、政治と経済にしっかりと興味を持って過ごすことが今後より大切となります。
シュリンクフレーション 消費者をだます隠れたインフレ
シュリンクフレーションという言葉があります。
シュリンクとは縮小という意味であり、何が縮小されるかと言うと1包装当たりの内容量です。
昔はポテトチップス一袋を買うと、1回では食べきれず、2回に分けて食べたり、複数人で分けて食べたりすることが多かったと思います。
しかし、今ではポテトチップスを買っても一人で簡単に食べてしまえる量になっています。
また、カントリーマアムは明らかに小さくなりましたし、牛乳は1Lから900mLになってしまった。
コンビニの弁当を買うと、昔はお腹いっぱいになったのに最近はなんか物足りない。
そして一番胸糞悪いのが、適当な理由を付けて量を減らすことを企業側が正当化してくることですね。
「女性が消費しやすい量にしました」、「利用しやすい量に変更しました」などの文言ですね。
大体はこれらの言葉は増量ではなく、減量する時に使われます。
シュリンクフレーションは値段が変わらずに入っている量を減らすため、実質上の値上げになります。
そのため、ステルス値上げと言われたりもしています。
なので、値段が変わらなくてもシュリンクフレーションが起きていれば、価格の上昇がなくてもインフレは起きています。
シュリンクフレーションは日本がデフレと言われている時期でもひそかに起きてきました。
特に2010年代が顕著で、この時期に商品を買うと、今まで感じなかった何か物足りない感を感じることが多くなったのではないかと思います。
なので、日本が今まで長年デフレの時期にあったというのは正確ではなく、2010年代くらいから緩やかなインフレが起き始めて、2020年代に入ってから値上げが一般化されてインフレが本格化したととらえるのが正解ではないでしょうか?
まとめ
今回はインフレ、デフレ、スタグフレーション、シュリンクフレーションについてお話ししました。
学校の社会の授業で習うような内容ですが、用語の意味を正しく覚えていつインフレが起きて、いつデフレが起きるなどを把握できると、投資や貯蓄の計画を立てやすく、お金の管理がしやすくなります。
なので、お金に関係がある話ととらえて、いま日本がどんな状況なのか、きちんと見極めて投資や貯蓄の計画を立てていくようにしましょう。
今回のお話は以上となります。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
