ふるさと納税と聞いて節税という言葉を思い浮かべる人もいると思いますが、実際は節税ではなく、税金の先払いの制度となります。
ただ、ふるさと納税には返礼品というものがあります。
返礼品があることで、ふるさと納税がただの税金の先払いではなく、ふるさと納税をした自治体から送られてくる特産品を楽しむことがお得な制度になっています。
自己負担額は二千円で、それ以上は返礼品の価格の分だけお得に返礼品を楽しめます。
そんなふるさと納税について説明したいと思います。
※この記事には広告を含んでいます
この記事では以下のことが書かれています。
ふるさと納税は厳密には節税ではなく税金を先払いする制度であること
ふるさと納税がお得なのは、寄附に対する返礼品が送られてくるから
ふるさと納税は上限額があり、年収と家族構成で上限が決まる
サラリーマンは確定申告をせずに済むワンストップ特例制度が利用できる
目次
ふるさと納税とはどんな制度か?
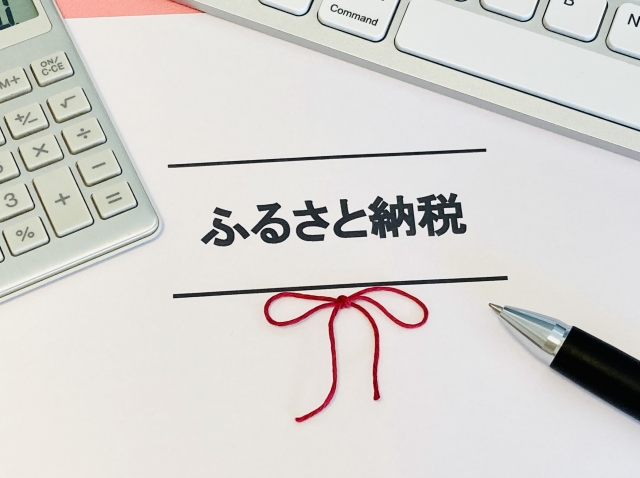
ふるさと納税とは、寄附にあたるもので、自分が住んでいる市や町以外の自治体に寄附を申し込むとその地方で作られた特産品が送られてきます(自分が住んでいる市や町に寄附しても返礼品は送られてきません)。
そして、その特産品は様々なものがあり、民芸品から日用品、食料品まで様々です。
ふるさと納税の初期の頃は、返礼品という考え方がなく、ただ自治体に寄附するだけのものでした。
しかし、ある自治体が返礼品をつけたことで、その考え方が他の自治体に広がり、返礼品を用意してくれる自治体がほとんどである状態となったのです。
そして、返礼品を受け取ることで実質ある程度の寄附金のキックバックが行われる状態となり、ふるさと納税がお得な制度と認識されるようになりました。
特に注目するところは、ふるさと納税は税金の控除対象となるところで、ふるさと納税を行うと自己負担二千円で、それ以上は所得税と住民税が控除されます。
そのため、実質的には税金を先払いする制度ともいえるのですが、無限に控除されるわけではなく、上限があるのできちんと上限を守らないとそれ以上は自己負担となってしまい、最大限に制度を活かすことが出来ません。
もちろん、上限を下回っても、上限までの差額の分、所得税、住民税の控除が少なくなってしまいます。
例えば独身の人が四万円寄附する三万八千円が税額の控除・還付の対象となります。
この上限額は家族構成や年収で変わってきますので、あらかじめ上限額を把握してから計画的にふるさと納税を行うと良いでしょう。。
上限の知り方はふるさと納税のサイト(さとふるなど)で、年収を入力するといくらまでが上限ということが分かるページがあるので、利用してみると良いでしょう。
ふるさと納税は返礼品の還元率の制限や、2025年9月からはポイント還元の禁止など利用者にとって不利な制度に改悪されていく傾向がありますが、それでもふるさと納税はお得な制度であることに変わりはないので、返礼品の廃止などでお得な制度でなくならない限り、利用する価値は十分にあります。
ワンストップ特例制度
サラリーマンにうれしい制度としてワンストップ特例制度があります。
本来は寄附金控除の申請には確定申告が必要なのですが、ワンストップ特例制度を使うと、送られてきた申請書に記入してふるさと納税を行った自治体に送るだけで済みます。
ただし、制限があり、最大5つの自治体までの寄附であること、そして確定申告するべき収入があればワンストップ特例制度を利用することが出来ません。
ワンストップ特例制度を利用できない場合は、確定申告で寄附控除欄を記入して申請しましょう。
また、外国株の配当がある場合、医療費控除がある場合など、確定申告で控除対象になるものがある場合もワンストップ特例制度を使わず、確定申告をした方がお得になります。
事業主ではない限り青色申告は使えませんので大抵の場合は白色申告での確定申告になりますが、そこまで難しくないので抵抗感を持たずに確定申告で得するものがあれば、積極的に確定申告を行うと良いでしょう。
お勧めはe-taxです。
アプリやアドオンなどを入れる必要がありますが、わざわざ税務署に行かずに自宅から確定申告が出来るので、税務署に行くために有休をとる必要がありません。
ふるさと納税はなぜ節税ではないのか?
ふるさと納税が節税になるかと聞かれると、個人的には節税にはならないと答えます。
理由は、所得税、住民税はしっかりと別の自治体に支払ったことになるからです。
そのため、所得税、住民税の総額は変わらず、しかもふるさと納税したうちの二千円は控除対象になりません。
全く返礼品がないふるさと納税の場合、ただの住民税の先払いとなり、しかも二千円は自腹で寄附することになるので、損をすることになります。
しかし、寄附金に対する返礼品があると状況が変わってきます。
一万円の寄附をすると大体二千円から二千五百円くらいの価値の返礼品が届くのが普通です。
ふるさと納税の合計金額が四万円くらいになると、大体一万円くらいの価値の返礼品を受け取ることになります。
そのため、自己負担額を除いても数千円くらいの得になり、特に普段使うものを返礼品として選んだ場合は、スーパーなどで返礼品の価格の分だけ買い物をする必要がなくなるので、家計の節約になります。
そのため、ふるさと納税は節税とまでは行かないまでも(買い物をしない分の消費税は浮きますが)返礼品をもらうことでお得な制度となるため、家計の節約を考える場合は上限までしっかり使い、確定申告やワンストップ特例制度を忘れずに行うことを心掛けるといいでしょう。
ワンストップ特例制度を確定申告が必要なのに利用したり、ワンストップ特例制度の際に提出する書類を出さなかったり、確定申告が必要なのにやらなかったりすると支払う住民税と所得税が控除されないため、確実に必要な手続きを行うことを意識しておきましょう。
ふるさと納税の返礼品は何を選んだらいいか?

ふるさと納税では様々な返礼品を選べます。
何を選んだらいいか分からない人もいると思いますが、基本的には自分が欲しいものを選んで問題はないと思います。
こちらの記事でおすすめの返礼品を紹介していますので、参考にして頂ければと思います。
基本的に自分が欲しいものを選ぶといいとは言いましたが、米、肉、ウナギなどの人気の返礼品は値段の割に量が多いものもあり、お得感が増します。
ただし、一人暮らしの場合、食べきれない量の返礼品を受け取ることになることもあるため、慎重に返礼品を選んだほうがいいかと思います
自分が食べ切れるようなもの、使い切れるようなものを選んで、地域の特産品を最大限有効利用するようにしましょう。
自分が行っているように、土用の丑の日用のウナギや、ちょっとした贅沢のためにマンゴーを返礼品に選ぶのもありです。
この辺りはふるさと納税を行う人の裁量で決めていけば良く、節約ばかりに意識を向けても面白くないため、うまく贅沢と節約のバランスが取れた返礼品の選び方をすればいいのではないかと思います。
ふるさと納税の二千円の負担について
ふるさと納税の自己負担額の二千円ですが、これは各自治体に寄附を行うとその都度発生するのかというと、そうではありません。
各自治体の寄附の合計金額から二千円を引いたものが控除・還付の対象となります。
そのため、寄付をする自治体が複数となっても特に損をすることがありません。
むしろ、複数の自治体に分けてふるさと納税を行う方が色々な返礼品を受け取る楽しみ方が出来ていいのではないかと思います。
ふるさと納税は、正しく知って正しく使うことが大事
ふるさと納税は制度を正しく知ったうえで利用すると、メリットを最大限活かせます。
ふるさと納税を正しく理解してしっかり使いこなしていくことで、お得に特産品を手に入れ、ふるさと納税を最大限有効活用しましょう。
本業以外に収入のないサラリーマンであればワンストップ特例制度がお勧めで、確定申告よりも簡単に手続きを行うことが出来ます。
本業以外にも収入があったり、控除対象があったりする場合は確定申告で寄附金控除を申告するといいでしょう。
ふるさと納税の控除の上限額は年収と家族構成で変わってくるので、ふるさと納税をする前に必ずシミュレーションをして上限額を確認しておきましょう。
そして、計画を立てて利用し、出来れば上限額までしっかりと利用するのが理想的なふるさと納税の利用方法となります。
ふるさと納税のおすすめサイトは以下の通りです。
ポケットマルシェのふるさと納税
産直品に強いふるさと納税サイト。
ふるさと納税を申し込んでから届くまでが早く、農産物の返礼品を探す場合はここがおすすめ
さとふるのふるさと納税
以下の実績を持つ、ふるさと納税のメジャーなサイト
認知度No.1 ※1
利用したいサイトNo.1 ※1
お客さま満足度90%以上 ※2
※1 2024年1月時点 調査実施機関:(株) インテージ
※2 2024年2月時点 自社調べ さとふるサイトユーザー対象
ふるなびのふるさと納税
ふるさと納税をするとコインが貯まる。
貯まったコインをAmazonギフトカードや楽天ポイントなどに交換することが可能。
今回のお話は以上となります。
最後まで読んで頂きありがとうございました。

